AIやSNSをビジネスで
使う前に確認すべき
「著作権」と「商用利用」
の落とし穴。
知らなかった…では済まされない
重要ポイントをやさしく解説します。
知らなかった…じゃすまされない!AI・SNS活用前に確認すべき“著作権と規約”のはなし
この記事がおすすめの方
・AIツールを使い始めたばかりの方
・AIを使い始めたけれど、
何が商用利用OKなのか不安な方
・SNSやYouTubeなどの発信に
AIを活用している方
・クライアントの代わりに
コンテンツを作る機会がある方
はじめに

昨日は、ChatGPTで4コマ漫画が
描けるようになった!
というブログを書きました。
AIやSNSのおかげで色々なことが
できるようになってきた今、
これらのツールは
個人ビジネスにとって心強い味方です。
私自身も、文章の下書き、画像制作、
動画編集、投稿作成などに日々活用していて、
なくてはならない存在になっています。

でも、「便利=自由に使っていい」
とは限りません。
特に商用利用やクライアント案件では、
「著作権」「利用規約」などの
確認を怠ると、大切な“信頼”を
損ねてしまうリスクもあるんです。
こんなことを考えたことないですか?
- 「AIで作った画像を使ったら、
著作権って大丈夫?」 - 「商用で使っていいの?」
- 「自分で使うのはいいけど、
クライアントの案件に使っても問題ない?」
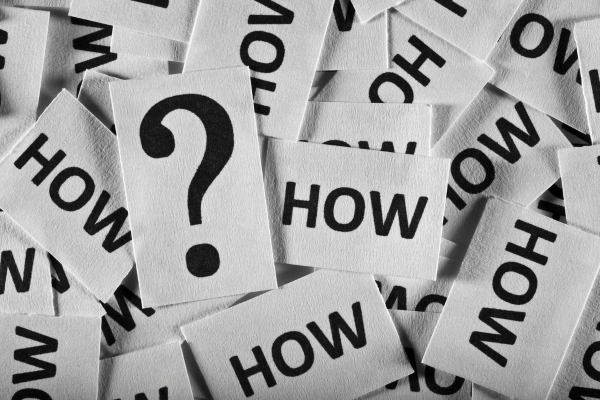
私たちのような個人で
仕事をしている立場では、
「ツールの使い方」そのものが、
信用や信頼に直結する時代
になってきています。
SNSやAIの“便利さ”に
頼りきるのではなく、
著作権や利用規約などの
ルールを理解した上で、活用すること。
それこそが、これからの時代に
“選ばれ続ける人”になるために、
大切な意識なのではないかと感じています。
本日のブログでは、
AIやSNSを活用する際に、
特に気をつけたい著作権と
利用規約のポイントについて、
お伝えします。
生成系AIと著作権:知っておきたい基本ポイント

文化庁と内閣府は、
AIの進化に対応し「AIと著作権」
に関する資料を公開しています。
中でも押さえておきたいのが
「2つの段階」での考え方。
ちょっと難しいけれど、
資料を見てみましょう。
開発・学習段階
データセットを学習に利用して、AI(学習済みモデル)を開発AI開発のような情報解析等において、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為
※ 1 は 、原則として著作権者の許諾なく利用することが可能
※1 例えば、3DCG映像作成のため
風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられるただし、「必要と認められる限度」を超える場合や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合※2」は、この規定の対象とはならない。
※2 例えば、情報解析用に販売されているデータベースの著作物をAI学習目的で複製する場合など
出典:文化庁「AIと著作権の関係等について」
難しいですよね…
解説していきましょう。
AIを作るときや、
賢く育てるためには、
画像や文章など、
たくさんの“見本”を読み込ませて
学習させることがあります。
このとき使われるのが、
すでに世の中にある作品
(=著作物)です。
たとえば、プロの撮った写真や、
小説、ブログ記事なども、
学習に使われることがあります。
でもこの段階では、
作品を楽しむためではなく、
“AIの頭を良くするために
使っているだけ”なので、
基本的には著作権者の
許可なしでもOKとされています。
ただし注意が必要なのは、次のような場合は
注意が必要です。
- 明らかに必要以上の量を使っている
- 著作物の売上や価値に悪い影響を与えてしまう
こんなときは、
「AIの学習目的だから」といっても、
許可が必要になることがあります。
※「思想や感情を楽しむ」とは?
作品を見て心が動いたり、
考えさせられたりする
“人の感情の体験”のこと。
学習のために写真や小説を読み込むのは、
「作品を楽しんでいるわけではない」
=人のように感動したり考えたり
していないから、
著作権的にはセーフというわけです。
生成・利用段階
AIを利用して生成した画像等をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、著作権法で利用が認められている場合※を除き、通常の著作権侵害と同様
※ 個人的に画像を生成して鑑賞する行為(私的使用のための複製)等
生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性
(創作的表現が同一又は類似であること)や依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなる
出典:文化庁「AIと著作権の関係等について」
こちらも解説していきましょう。
AIが作った画像や文章を
ブログやSNSで公開したり、
商品ページやLPなどで
商用利用したりする場合、
通常の著作権のルールが適用されます。
例えば
・ すでにある誰かの作品に
そっくりな見た目になっている
・ その作品を参考にして真似た
と判断されるような内容
それは「著作権侵害」と
見なされてしまう可能性があります。
だからこそ、
AIで作ったものを使うときは、
“他の作品と似すぎていないか”
をしっかり確認することが大切。
参考:文化庁「A I と著作権」
〈文化庁/動画〉もご参考に
令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」
「ジブリ風」「シャネル風」は注意が必要!

上記で、学習段階では
写真や小説を読み込むのは、
「作品を楽しんでいるわけではない」
=人のように感動したり考えたり
していないから、著作権的にはセーフ。
でも、生成・利用段階、
AIが作った画像や文章を
ブログやSNSで公開したり、
商品ページやLPなどで
商用利用したりする場合、
通常の著作権のルールが適用。
という説明をしました。

3月26日以降画像生成の
機能がアップして、
感動するような画像が
カンタンに作れて嬉しくて
「ジブリ風の画像が描けました!」
とSNSに載せている方を
ちらほら拝見しました。
実はこれ、
著作権NGの可能性が高いのです。
「ジブリ風」は、スタジオジブリの
絵柄・世界観に著作権があるため、
著作権・商標権の侵害になる
リスクがあります。

ほかにも例えば、
「シャネル風のカバン描いて」
とAIにお願いして、
シャネルのマークが入った画像を描き、
SNSにアップしたとします。
「シャネル風」は、シャネルの
デザイン・スタイル・ブランド名が
商標登録されており、
特定ブランドを想起させるデザインは
トラブルのもとになる可能性が高いです。

SNSの投稿、LPやバナー制作、
YouTubeのサムネイルなどに
使う場合も、注意が必要です。
そのほかにも、
こんなケースは危ないかも…
- 有名人の書き方を真似した「○○風文章」
- 他サイトそっくりの構成・語句
- 特定ブランドや作品に似た構図・スタイル
AIの利用が「著作権侵害」にあたるかは、
①独自性が似ている
②参考にした・見て模倣した
の両方が認められると、
違反と判断されることがあります。
ビジネスに使うなら“自分の表現”が大事

AI生成物、SNSを活用するなら、
以下のような意識がポイントになります。
①作風を真似しすぎない(画像、文章生成)
「〇〇風にして」と指示することは
技術的には可能ですが、
他人の作品に似すぎると
著作権や信頼の面でリスクがあります。
参考程度にとどめ、
自分らしいタッチに調整しましょう。
②自分の体験や考えを加える(文章生成)
「なぜこの内容を伝えたいのか」
「私が実際にやってみた結果は?」
など、“自分にしか書けないこと”を
加えるだけで、グッと信頼される発信に。
③使用ツールの「商用利用可否」の確認
今の時代、CanvaやCapCut、ChatGPTなど、
便利なツールを使えば、デザインも、文章も、
動画も“かんたん”に作れるようになりました。
でも、自分のビジネスやクライアントワークで
使うなら、必ず自分が使うツールが
商用利用可能かどうか確認しましょう。
こんな“うっかり”に気をつけて!

- Capcutで動画作って、
クライアントに動画を納品したけど、
無料版は商用利用禁止だと後で知った。 - YouTubeで流したBGM、
あとで著作権警告が来た…
これ、よくあるトラブルです。
知らなかったでは済まされないので、
「使う前に確認」が鉄則!
「みんなが使ってるから大丈夫」ではなく、
「今、この条件で本当に使っていいか」
を確認する習慣を持ちましょう。
さいごに 信頼される発信者・制作者になるために

AIもSNSも、私たちの味方です。
でも、“便利な道具”だからこそ、
「どう使うか」でその人の信頼
が決まる時代になってきたと思います。
- 誤解を招く表現になっていないかな?
- 著作権を守ってるかな?
- クライアントに安心してもらえる
説明ができているかな?
そんな視点を持つことで、
あなたの発信・あなたの作品が、
より信頼されるものに
なると考えています。
AIやSNSはとても便利だけど
使い始める前には、
規約をまずみてみましょう。
商用利用可能かどうかも
プランによって違うことも
よくあることです。

私の使っているツールはどうかな?
と思ったら、
例えば「YouTube 規約」
と検索してみてください。
内容がよくわからないと思ったら、
ChatGPTに要約してもらったり、
それでもわからない場合は、
「YouTubeでの商用利用について
見解を教えて」と聞いてみると
いいと思います。
それでもわからず、
自分で判断できない場合は、
専門家に相談しましょう。
時代の変化が早いので、
私たちもそれにしっかりついていき、
「調べ、考え、判断する」
スピードをアップさせることが大切ですね。
本日も最後までご覧いただき
ありがとうございました。





コメント