AI時代に欠かせない2つの力とは?
情報も人の力も、
引き出せる自分になるヒントを
解説しています。
AI時代に生き残るのは○○力がある人!個人事業主が磨くべき2つの力とは?
この記事がおすすめの方
- ChatGPTを使ってみたけど、
うまく質問できない - 調べても答えにたどり着けず、
いつも迷子になる - AIの進化に焦っているけど、
何をすればいいかわからない - お客様の本音を引き出せず、
会話が浅く終わってしまう
はじめに
ChatGPTをはじめとする
AIツールがどんどん賢くなり、
「文章も画像もAIが作ってくれる
困っていたらアドバイスもしてくれる」
という時代が、
すでに当たり前になってきました。

でも、それと同時に
こんな声もよく聞きます。
・AI、便利そうだけど、
どう使っていいかわからない…
・質問の仕方がわからなくて、
思ってた回答と違った
・調べたつもりなのに、
いつも“答え”にたどりつけない
そう、
“検索して”“聞ける力”がないと、
AIすら使いこなせない時代
がすぐそこに来ているのです。
このブログでは、
そんな時代に生き残るために大切な
2つの○○力、
「検索力」と「質問力」
についてお伝えします。
① 検索力とは?=「自分の知りたいことに近づく力」

今や、私たちが「わからない」
と思うことの多くは、
ネット上にすでに答えが出ています。
けれど実際には、
「どう調べればいいかわからない」
「どんなキーワードを入れればいいのか思いつかない」
という方も少なくありません。
ここで必要なのが、
“言語化力”=心の中の感覚や
考えを“言葉”で表せる力です。
自分の中のモヤモヤや疑問を、
どれだけ言葉にできるか。
その精度が上がるほど、
GoogleでもChatGPTでも、
ほしい答えに近づけるのです。
言語化を伸ばすにはどうしたらいいのか?
をご紹介したいと思います。
言語化力を伸ばす5ステップ
①「なんで?」を3回くり返す

モヤモヤした時は、まず自分に質問してみましょう。
「SNSがしんどい」
→ なんで?
→ 「投稿に時間がかかる」
→ なんで?
→「何を書いていいか分からない」
こうして“本当の原因”を掘り出すことで、
自然に言葉が見えてきます。
② 1日1つ「気持ち」を書く

日記じゃなくてもOK。
「今日はなんだか気が重い」
「ちょっと達成感」など、
一言でもいいから
“気持ち”に名前をつけて
書いてみることが大切です。
感情に言葉を与える習慣が、
言語化力の筋トレになります。
③ 小さな違和感に“名前”をつける

「なんかモヤっとする」
だけで終わらせずに、
「自分だけ頑張ってる気がしてイライラ」
「なんとなく空回り感」
など、感覚に“名前”をつける練習を
つけてみてください。
それだけで、
自分を整理しやすくなり、
他人にも伝えやすくなります。
④「言葉のストック」を本から仕入れる

読書は、表現力を磨く最高のインプット。
・ 読みやすいエッセイ
・ 自分と似た世代の著者の本
・ 心に刺さるフレーズをメモするだけでもOK
“こんな表現あるんだ”という気づきが、
あなたの言葉の引き出しを
増やしてくれます。
⑤ 書いたものを「読み返して」整える
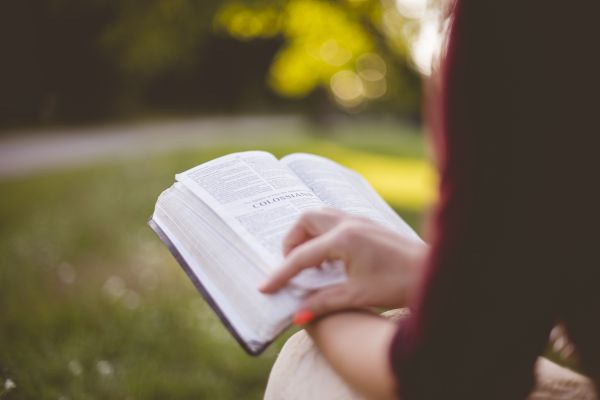
書きっぱなしではなく、
1日〜数時間後に読み返すことで、
「もっとこう言えば伝わるな」
と気づく感覚が磨かれていきます。
SNS投稿やブログ、メモなど、
小さなアウトプットの見直しを
習慣にすると、表現力がぐんと伸びます。
質問力とは?=「自分のほしい答えを引き出す力」
そして、調べてもなお不明点があるとき
次に必要なのが、質問力です。
質問力とは、
ただ「聞く」ことではありません。
「どう聞くか?」
「相手にどういう情報を伝えるか?」
そこに、その人の思考の深さや、
配慮がにじみ出ます。
ここで、わかりやすく
旅行どこに行くかの質問で見てみましょう。
良い質問の例

「今度、40代の女友達と
リフレッシュ旅行に行きたいんです。
温泉に入って、ゆっくり自然の中で
過ごせる場所を探しています。
候補として箱根・湯布院・
南紀白浜を調べました。
私は湯布院が静かで景色もいいなと
思っているんですが、
〇〇さんのおすすめはありますか?」
この質問、すごく答えやすいと思いませんか?
なぜなら…
ポイント分析

- 目的が明確
→ 「リフレッシュ旅行」だとわかる - 誰と行くかがわかる
→ 40代の女友達と(ターゲットが絞れてる) - やりたいことが具体的
→ 温泉&自然でのんびり - 自分で調べた努力がある
→ 候補3つ出している - 自分の意見もある
→ 湯布院がいいと思っている - 相手に求めていることが明確
→ 「あなたのおすすめは?」と聞いている
悪い質問の例

「どこかいい旅行先ない?」
これだと、相手は…
- 誰と行くの?
- 何日くらい?
- 何がしたいの?
- 予算は?
- 海?山?国内?海外?
と、逆に質問しないと
答えられらないですよね。
お友達だといいかもしれませんが、
結果、「ちょっとめんどくさいな…」
と思われてしまうことも。
なんとなく、掴めたところで
デザインについて相談したい場合の
“いい質問”と“悪い質問”を
比べてみましょう。
良い質問の例

〈40代女性飲食LPの配色について〉
40代女性向けの飲食店LPを
制作しているのですが、
喜ばれる配色にしたいと思っています。
配色について3つ候補を調べてみました。
私は①が一番元気な印象で
良いと感じています。
先生のご意見をお聞かせ
いただけますでしょうか?
このような質問をされると、
「この人、よく考えているな」
「ちゃんと思考を整理できているな」
と感じます。
方向性も明確で回答も早くできますし、
思わずプラスで何か教えて
あげたくなっちゃいます。
悪い質問の例

デザインがうまくいきません。
アドバイスください。
このような質問だと、
・どんな目的で作っているのか?
・誰に向けたものなのか?
・何がどううまくいかないのか?
が全く見えないため、
聞かれた側がいくつも
確認しなければなりません。
その結果、返信が遅くなったり、
具体的なアドバイスを得にくかったり。
何度もこんな感じで聞かれると
最悪の場合、「面倒な人だな」
と思われてしまうことも…
③ 質問の仕方には“品格”も出る

これはAIに対してだけではありません。
コンサルの先生や仲間に
質問する時でも同じです。
「この人、何も調べずに聞いてきたな」
と思われるか、
「調べたうえで確認のために聞いてるな」
と思われるか。
その違いは、
質問の文章を見れば一瞬で伝わるのです。
これはある意味、相手への気遣いでもあり、
相手の時間や労力への配慮、
誠実さの表れでもあります。
まとめ:検索力と質問力があれば、AI時代も怖くない

AIの進化が加速する今、
「検索力」と「質問力」は、
ますます重要になっています。
ChatGPTなどのAIも、
ただ使うだけでは意味がなく、
「何をどう聞くか?」
が求められる時代です。
自分の考えを整理した上で
質問できる人は、相手からも信頼され、
「この人にはちゃんと応えたい」
と思ってもらえる存在に。
検索力と言語化力を味方につけて、
迷わず、あなたらしい
一歩を進んでいきましょう!
一足飛びでは身につかず、
脳の筋トレが必要なので、
今から始めるのがおすすめです。
本日も最後までご覧いただき
ありがとうございました。

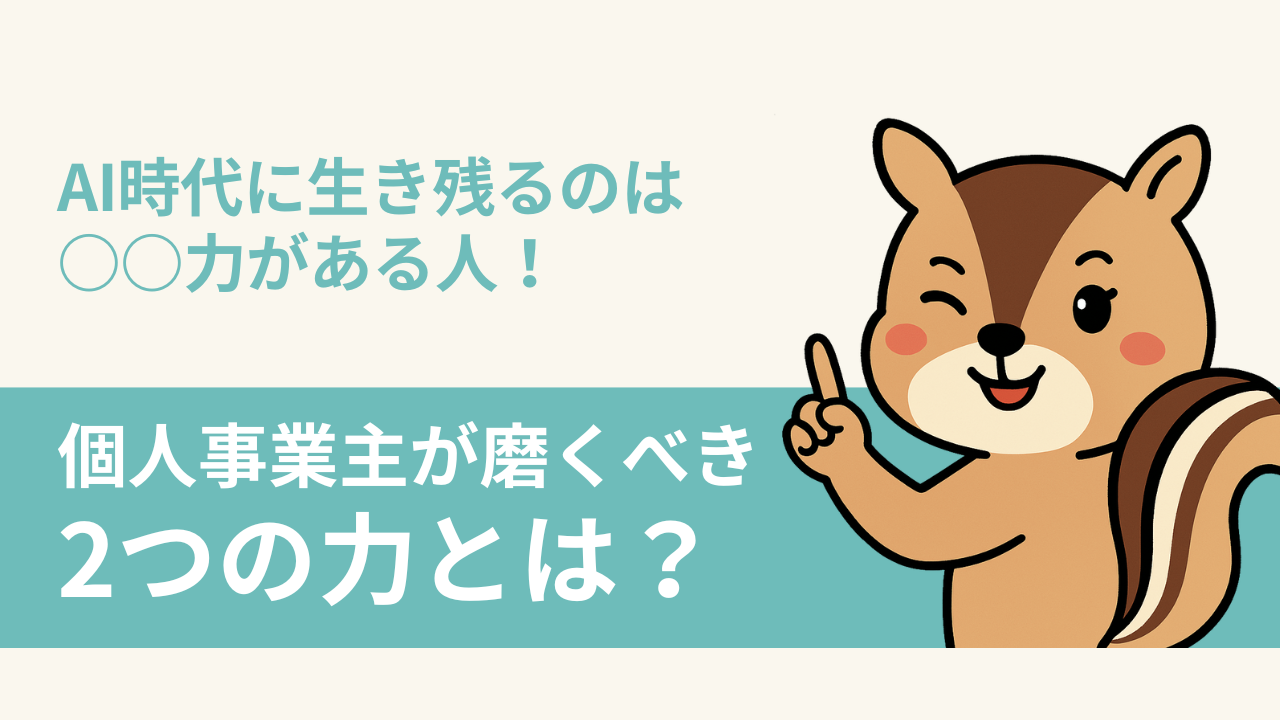

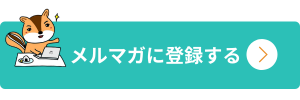

-11-120x68.gif)
コメント